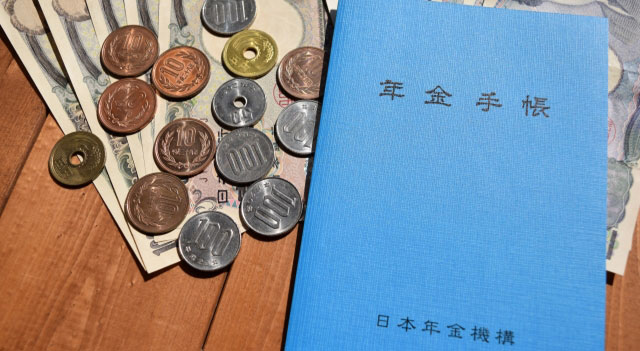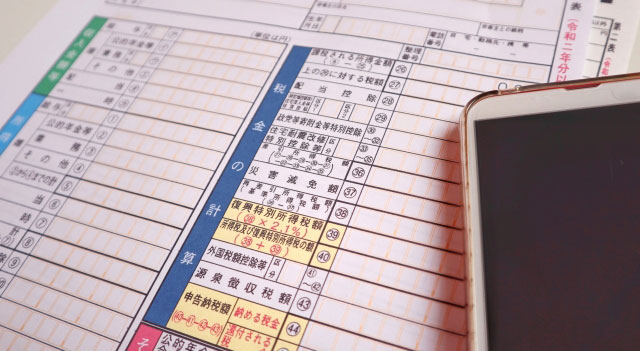最近、「ポイ活」という言葉を耳にするようになったという人が多いのではないでしょうか?
「ポイ活」とはポイント活用を意味する略語で、ポイントを貯めたり使ったりすることで節約に役立てる1つの手段として確立しています。
本記事では、ポイント活用で節約するためには一体どういった方法を取れば良いのか、おすすめのポイント活用術についてまとめていきます。
【ポイント活用術】ポイント活用のメリット・デメリットは?
まずポイント活用でうまく節約していくための方法を解説する前に、ポイント活用のメリットとデメリットについてみていきましょう。
ポイント活用のメリット

ポイント活用のメリットは、普段の買い物で貯めたポイントを別の買い物をする時やクレジットカードの支払いに充てることができる点です。
ポイント活用で貯めたポイントをうまく使えば節約術の1つとして活用することもできます。
ポイント活用のデメリット
ポイント活用最大のデメリットは、複数種類のポイントを管理するのが面倒という点です。
このポイントを使うというものを絞った上で買い物をしていかないと、ポイントが放置されてしまいます。
また、ポイントを貯めることに意識が向きすぎると、節約どころかかえって無駄にお金をつかってしまうため、自分のライフスタイルの範囲内でポイント活用を行って節約を心掛けていくのが大切です。
【ポイント活用術】ポイントをうまく貯める方法
ポイント活用のメリットとデメリットを知ったところで、早速ポイント活用で節約する方法についてみていきましょう。
まずはポイントをうまく貯める方法についてまとめていきます。
その1. ポイントの二重取りを狙う
ポイントの二重取りとは、一回の支払いで2種類のポイントを獲得することを意味します。
例えば、ショッピングモールで買い物をする時、そこで発行するポイントカードと、買い物をしたショップが発行しているポイントカードを支払い時に提示して買い物をすることでポイントの二重取りができます。
少しでも多く1回の支払いでポイントを獲得できれば、節約に使えるポイントが増えるため、必ず知っておいた方が良い知識です。
また、ポイントは二重取りだけでなく、三重取り、四重取りすることも可能です。
三重取りなら、先ほどの例での支払いをクレジットカードにすることで、そのカードのポイントが貯まり、四重取りなら、クレジットカードでチャージした電子マネーで支払いをすることで、電子マネーで支払ったポイントも獲得できます。
最近だと、QRコード決済が普及したことでクレジットカードを持っていない人でも、ポイントの複数取りがしやすくなりました。
その2. 貯めるポイントの種類を絞る
ポイント活用のデメリットで触れたように、何種類もポイントを貯めていると管理が難しくなり、無駄になるポイントも出てくる可能性があります。
これではうまく節約するためにポイント活用をしているとは言えません。
ポイント活用で大切なのは、貯めるポイントをよく利用するお店のポイントに絞ることです。
ただ、その店舗独自のポイントだと他店舗で扱えないため、なるべくTポイントやdポイントといった共通ポイントを貯めるようにしましょう。
共通ポイントを貯めるように意識すると、それに合わせたクレジットカードを使うこともできるため、ポイントの複数取りがしやすくなります。
その3. 固定費の支払いでポイントを獲得できるようにする
節約を意識してポイント活用をするために重要なことが、必要不可欠な費用からいかにポイントを生み出すかということです。
必要不可欠な費用といえば、電気代や水道光熱費、家賃、通信費、保険料などが挙げられますね。
最近では、公共料金などがクレジットカード払いに対応していて、ポイント活用を用いた節約がしやすくなりました。
例えば、ENEOSでんきだと電気料金200円(税別)につきTポイントが1ポイント付与、東京電力だと電気料金1,000円(税別)につき5ポイント付与となっています。
クレジットカード払いにすればポイントが二重取りできますね。
ちなみにどちらも変わらないように思えますが、電気料金200円で1ポイントが入る分、ENEOSでんきの方がポイントが入りやすくて節約意識が高く、ポイント活用がうまいと言えます。
当然、貯めているポイントに合わせて電力会社を選択した結果、損していたら節約とは言えないので注意が必要です。
【ポイント活用術】ポイントをうまく使う方法
ポイントをうまく貯めることができても、うまく使えなければポイント活用で節約できているとは言えません。
節約することを特に念頭に置いて、ポイントをうまく使う方法についてみていきましょう。
その1. セールの期間にポイントを使う

貯めたポイントは実質タダで買い物ができるので、節約を意識するならポイントをいつも行く店舗がセールをしている期間に使うのがお得です。
例えば、ポイントが使える店舗で最も身近なところはコンビニが挙げられます。
コンビニでは様々な共通ポイントを使うことができる上、冬であれば肉まんがセールで安くなることがあります。
普段120円の肉まんが100円で買えるようになると、普段1個買った時と比べて20円分のポイントが節約できています。
これを5日間繰り返せば、6日目にも1個食べる余力が生まれ、食費を少し節約することができます。
これがポイント活用の真骨頂です。
その2. ポイントを投資に使う
少し前と比べると世間の投資に対する認識が少しずつ変わり、今では少額のポイントで投資ができるようになりました。
貯めたポイントを普段の生活に充てるのも節約ですが、ポイントを投資に使ってお金を増やすのも長い目で見て節約であり、最高のポイント活用だと考えることができますね。
ただ、少額投資がメインとなるため、何十年単位の長期投資としてポイント活用を行う意識を持っておくことが重要です。
その3. ポイントを他社ポイント・マイルなどに交換する
ポイントの種類によっては、他社のポイントやマイルに交換することもできます。
今からポイント活用をして節約しようと思ったけど、ポイントがあちこちで貯まって放置したままだからもういいと諦めていた人にもまだポイント活用をして節約を始めるチャンスはあります。
一度自分が獲得しているポイントを交換して、いくつかの種類のポイントやマイルに統一できるか調べてみてもいいですね。
きっとポイント活用を用いた節約意識が高まるきっかけになるでしょう。
【ポイント活用術】事例紹介
ここでポイント活用の節約術の事例を見てみましょう。
やめさん・30歳主婦(仮名)は、楽天ポイントでポイント活用した結果、夫婦で約2年間の間に100万ポイント以上獲得しました。
まずメインのカードを楽天カードにし、楽天で寄付すると大量のポイントがもらえるふるさと納税に手を付けました。
ふるさと納税ひとつ取り入れるだけでかなりの節約になりますね。
お買い物マラソンやSPU、楽天DEALといった独自の機能で、1度の買い物で獲得できるポイントの割合を高め、固定費の支払いも楽天ポイントが入るように切り替えました。
ポイント活用を意識して生活すると、ここまでポイントを獲得できて大きな節約ができることが伝わってきますね。
まとめ
普段生活している中で、何気なく入ってくるポイントは、些細なものだとないがしろにされてしまう傾向があります。
しかし、本気になってポイント活用を取り入れた節約術を実践すれば、何百万単位の節約ができることが実証されています。
これまでポイント活用を意識した節約をしたことがなかった人は、自分の生活状況を見つめ直してみて、自分に合ったポイント活用をした節約術を身に付けてみてはいかがでしょうか?