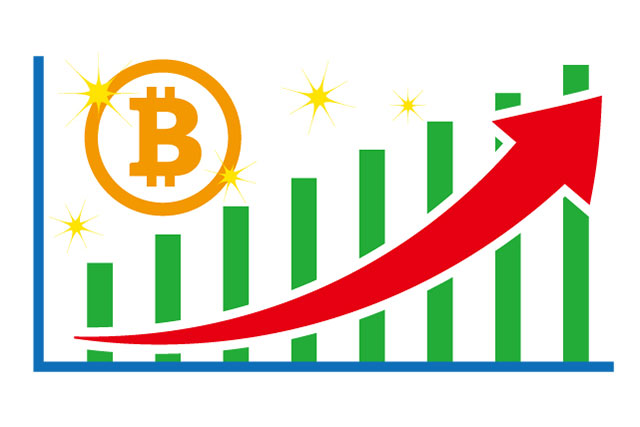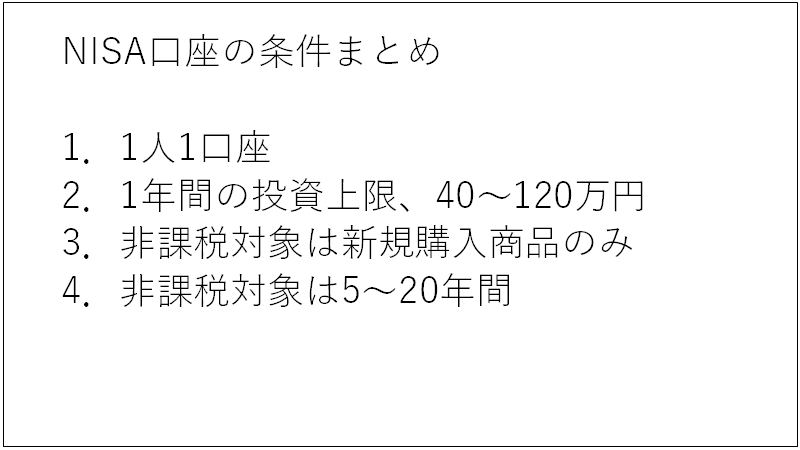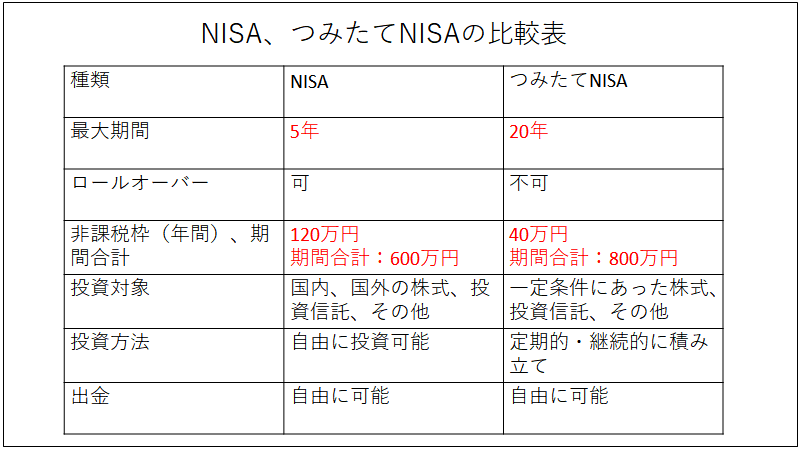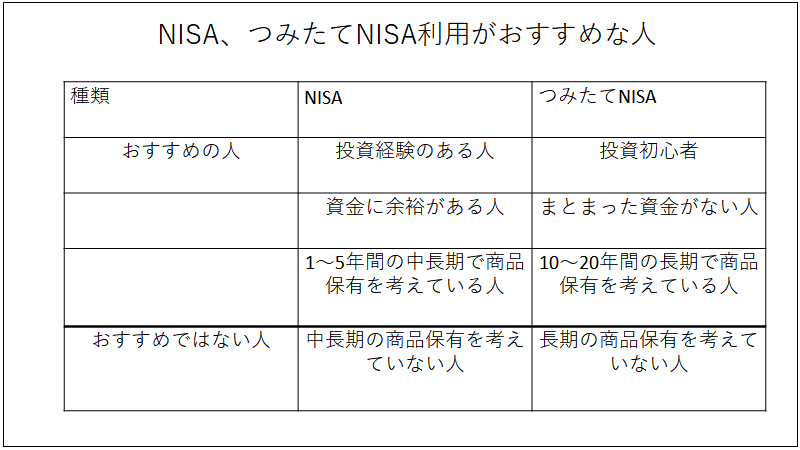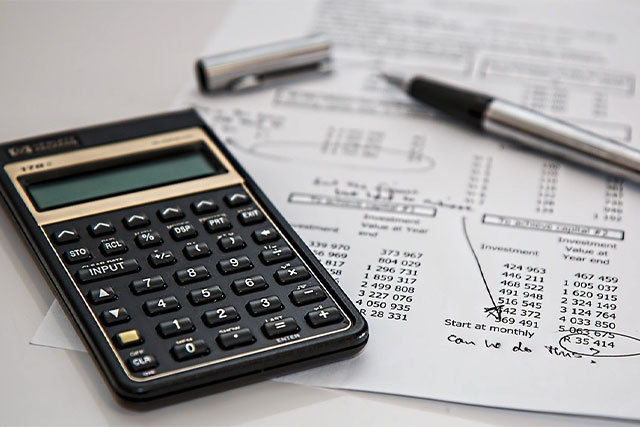人生において、大切な人に財産を相続したり贈与したりする場面は、いつの日か訪れます。しかし、相続や贈与には申告手続きが必要であり、それにともなって税金も納付しなければなりません。申告手続きで戸惑わないよう、今回は相続と贈与の概要をお伝えしていきます。
相続とは?

相続とは、亡くなった人が所有していた財産を特定の人物が引き継ぐことです。相続において、亡くなった人は「被相続人」と呼ばれ、財産を受け取る人は「相続人」と呼ばれます。
配偶者は必ず相続人となり、血族においては相続順位(優先順位)にもとづいて相続人が決まります。
法定相続では、財産の取得に関して相続割合が決まっているのも特徴です。たとえば、相続人が配偶者と子の場合、配偶者が1/2、子が1/2であり、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
ただ、不公平な遺言が残されると、相続人でも遺産が受け取れないケースも少なくありません。その点、遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の遺産取得を保障してもらえます。
ちなみに請求の期限は、遺留分権利者が相続と遺留分侵害の発生を知ってから1年以内です。
相続の手続き
相続手続きの流れは下記の通りです。
➀市区町村の役所に死亡届を提出する
②市区町村の役所や社会保険事務所などで、社会保険や年金に関する手続きを行う
③生命保険や損害保険に関して、保険金受取人が保険会社に請求する
④除籍謄本や改製原戸籍謄本などを調査して、民法にもとづき相続人を確定する
⑤被相続人の負債が多額であれば、相続放棄や限定承認をするために、家庭裁判所に申請する
⑥年金以外に、不動産所得等の収入があれば、税務署に準確定申告と税金の納付をする
⑦預貯金や有価証券、不動産、債務などを調査して、必要に応じて財産目録を作成する
⑧遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺言書があればそれに従って遺言執行者が手続きする
⑨払戻しや土地の名義変更などの相続手続きをする
⑩相続税を申告する必要があれば、申告をしたうえで納付する
※参考
除籍謄本:死亡や転籍、結婚などによって誰もいなくなった状態の戸籍
改製原戸籍:戸籍法が改正される前の様式で書かれた戸籍
限定承認:相続した財産から、亡くなった方の負債を返済して、余りがあれば相続できる制度
財産目録:保有する資産と負債を種類ごとにまとめた表
遺産分割協議:相続人全員で遺産の分割について協議すること
遺言執行者:遺言を正確に実現させるために手続きを行う各相続人の代表者
名義変更:法務局で管理されている登記簿の名前を変えること
相続税の計算方法
みずほ証券によると、相続税の計算方法は下記の手順です。
➀課税遺産総額から各相続人の相続税額(仮)を計算する
②相続税の総額を計算する
③各人の実際の相続税額を計算する
各人が負担する相続税の額は、各人が取得する遺産の割合に応じて按分して算出されます。わかりやすくまとめると、遺産をたくさんもらう人ほど、相続税が高くなるということです。
※参考
相続税の対策
相続税は対策によって節税できます。早速、相続税の節税対策を確認してみましょう。
対策1.税額控除を活用する
税額控除を活用することで相続税を減額できます。
具体的な控除の例は、相続人が20歳未満のときに適用できる「未成年者控除」、相続人が85歳未満の障害者であるときに適用できる「障害者控除」、前回の相続から10年経過しないうちに新たな相続が始まったときに使える「相次相続控除」などです。
税額控除は相続人や受遺者の状況によって適用の可否が決まります。それぞれの控除を受けるための条件を事前に把握しておくとよいでしょう。
対策2.相続人を増やす
基礎控除額とは、税金がかからない額であり、相続税を減らすための金額です。
相続税の基礎控除額は下記の通り計算できます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人
つまり相続する人の数が多ければ控除額が増えていきます。相続人を増やせる方法として挙げられるのが養子縁組です。養子は実子と同じ扱いを受けるので、法定相続人としてカウントできます。
贈与とは?

贈与とは、お互いの合意にもとづき、相手に無償で財産を与えることです。読み方は「ぞうよ」です。一般的な贈与では、財産の合計額が110万円を超えると課税されます。
双方に贈与の認識がなくても、借り入れを免除したり、財産を低額で売買したりすると、実質的に贈与を受けたとみなされるケースもあります。
贈与の手続き
➀贈与の目的を明確にして計画を立案する
②贈与の内容について受贈者と協議して合意を得る
③贈与契約の内容を証明できるよう、贈与契約書を作成して押印する
④財産の引き渡しや不動産に関する所有権の移転登記を行う
⑤必要に応じて贈与税の申告と納付を行う
贈与税の計算方法
国税庁によると、贈与税の計算方法は下記の手順です。
➀贈与された財産(その年の1月1日から12月31日までの1年間)の価額を合計する
②合計額から基礎控除額110万円を差し引く
③残りの金額に税率を乗じて税額を計算する
ちなみに贈与税の税率は、国税庁では速算表が用意されており、具体的な計算の際に活用できます。必要に応じて活用してみるとよいでしょう。
※参考
贈与税の対策
相続税と同様に贈与税でも、節税に向けた対策が知られています。贈与税の節税対策も確認しておきましょう。
対策1.毎年110万円ずつ贈与する
一般的な贈与の基礎控除は110万円であることから、毎年110万円の贈与をすれば贈与税がかかりません。つまり、子ども1人に毎年110万円を5年間贈与すれば、550万円を非課税で贈与できます。
ただし贈与契約で、一定の年数にわたって毎年贈与を受けることが約束されている場合、1年ごとの贈与だと認められないことがあるので注意してください。
対策2.非課税の特例を活用する
贈与では、贈与の目的によって非課税となる特例が存在します。たとえば、「教育資金の贈与の特例」です。親子間などで教育資金を贈与するとき、1,500万円まで非課税として認められる制度です。
ただし、30歳までに使われなかった金額については、贈与税が発生してしまう点に注意しなければなりません。
参考:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
対策3.相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税とは、親(被相続人)と子・孫(相続人)の間で、将来相続される財産を前渡しで贈与できる制度です。贈与される金額のうち2,500万円が非課税として認められます。
数千万円の金額が非課税になるというメリットがあるだけでなく、相続前に必要な財産を相続人に使用してもらえるというメリットもあります。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、通常の贈与制度を活用できなくなります。相続時精算課税制度は慎重に検討するようにしてください。
相続・贈与では期限を守って正しく申告しよう

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。たとえば、2月10日に亡くなった場合は12月10日が申告期限です。ちなみに相続税の納税期限も申告期限と同じです。
申告期限までに申告をしないと、本来の税金以外に加算税や延滞税がかかる可能性があります。
一方、贈与税の申告と納税の期限は、財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの期間です。相続税と同様に申告期限を守らないと、本来の税金以外に加算税がかかる可能性があります。また、納税期限に送れた場合、延滞税がかかる可能性もあります。
ちなみに、申告すべき金額をごまかしてばれると、余計に税金を取られるので、正確に申告しなければなりません。
このように相続・贈与では、知らないとトラブルになるルールもあります。相続・贈与の概要を最低限把握しておき、いざ当事者になったときスムーズに対応できる準備をしておくことが大切です。